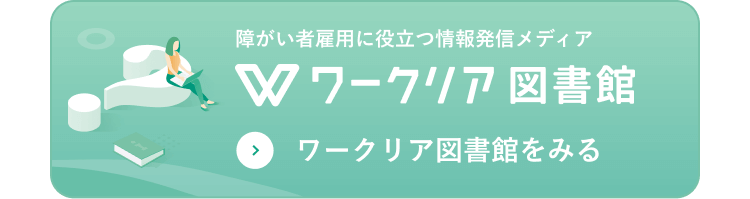法定雇用率を達成できなかった場合の「企業名公表」について解説
2025.01.07
2025.01.07

障がい者雇用義務のある企業が法定雇用率を達成できなかった場合、行政指導が行われます。その後に改善しきれないと、ペナルティとして行政により企業名が公表される可能性も。このコラムでは、雇用率達成指導の流れや、知っておきたい基礎知識をご紹介します。
法定雇用率について詳しく知りたい方は、下記の記事も併せてご覧ください。
(URL)https://worklear.jp/library/knowledge/3
目次
法定雇用率を達成できなかった場合の「企業名公表」とは?
「障害者雇用促進法」により、一定以上の規模の事業主は、従業員に占める障がい者の割合を法定雇用率以上にする義務があると定められています。
法定雇用率を達成できなかった事業主は、ハローワークから雇用率達成指導が行われます。
雇用率達成指導を受けても雇用状況の改善が特に遅れている企業は、厚生労働省により社名が公表されます。
この企業名公表は企業にとってリスクが大きいため、雇用状況は継続的に改善していくべきでしょう。
雇用率達成指導の流れ
法定雇用率が未達成だった場合の、雇用状況報告から企業名公表までの一連の流れを簡潔にご説明します。
雇用状況報告
従業員規模が40.0人以上の事業主は、毎年6月1日時点の障害者雇用の状況をハローワークに報告しなくてはなりません。
厚生労働省が定める記入要領に沿って、同年7月15日までに「障害者雇用状況報告書」を作成し、報告します。
雇入れ計画作成命令
雇用状況報告により法定雇用率が未達成だとわかり、かつ特定の基準に当てはまる場合、ハローワークから「障害者雇入れ計画作成命令」が発出されます。
その基準とは以下の通りです。
a 実雇用率が全国平均実雇用率未満であり、かつ不足数が5人以上の場合
b 実雇用率に関係なく、不足数10人以上の場合
c 雇用義務数が3人から4人の企業であって雇用障害者数0人の場合
上記のa・b・cのいずれかに該当すると命令が発出されます。企業は、命令発出後の1月1日から数えて2年間の「障害者雇入れ計画」を作成しなくてはなりません。
雇入れ計画の適正実施勧告
ハローワークから見て雇入れ計画の実施を怠っていると判断された場合には、計画の適正な実施を勧告されることがあります。
勧告される時期は、計画1年目の12月です。
特別指導
計画2年目を過ぎても雇用状況の改善が遅れている場合、9ヵ月間の特別指導の対象となります。
対象となる基準は以下の通りです。
・実雇用率が、最終年前年の6月1日時点の全国平均実雇用率未満
・不足数が10人以上
特別指導では、雇用義務達成を目標に、さまざまな雇用事例の提供や助言、求職情報の提供、面接会への参加推奨などが行われます。
企業名の公表
特別指導を受けてもなお雇用率が達成できない企業については、厚生労働省のWebサイトにて、報道関係者へ向けてその企業名が公表されます。公表後も指導は継続され、なお改善が見られない場合は再公表が行われます。
企業名公表による企業側のリスク
雇用率未達成により厚生労働省のWebサイトで公表されることには、以下のようなリスクがあります。
企業のイメージダウンにつながる
前項からわかる通り、企業名の公表はさまざまな指導を経た最後の段階です。
行政から何度も指導を受けた上で改善ができなかった、社会的責任を果たせなかった企業というイメージがステークホルダーに伝わり、不信感を抱かれる可能性があります。
インターネット上に情報が残り続け、世間へと広まる
企業名公表後は、厚生労働省のサイトだけではなく、さまざまな媒体に残り続けることが予想されます。
障がい者雇用を堅実に進めるには?
障がい者雇用の推進は企業の社会的責任を果たすために重要です。しかし、企業名の公表を恐れるあまり、体制を整えずに慌てて障がい者を雇用することは避けるべきでしょう。
まずはハローワークに相談したり、障がい者雇用に対する社内理解を深めたり、任せる業務の内容を決めたりして、障がいを持つ社員を職場に受け入れる準備を固めてから採用していきましょう。
まとめ
法定雇用率を達成できなかった場合の行政指導は、それ自体が障がい者雇用を始める良いきっかけにもなります。自社が社会的責任を果たせる企業であると証明することは、世間からのイメージアップにも繋がっていくでしょう。
ワークリアでは、障がい者雇用に関するお悩みや雇用後の体制構築など、企業様に向けたサポート全般を行っています。何から始めればいいかわからない企業様へも、0からサポートいたしますのでご安心ください。障がい者雇用に関してお困りの企業様は、まずはお気軽にお問合せください!

ワークリアとは
ワークリアは、障がい者専門の人材紹介サービスと障がい者雇用にまつわるコンサルティングサービスを運営しております。
障がい者採用にお悩みの方は、お気軽にご相談ください。